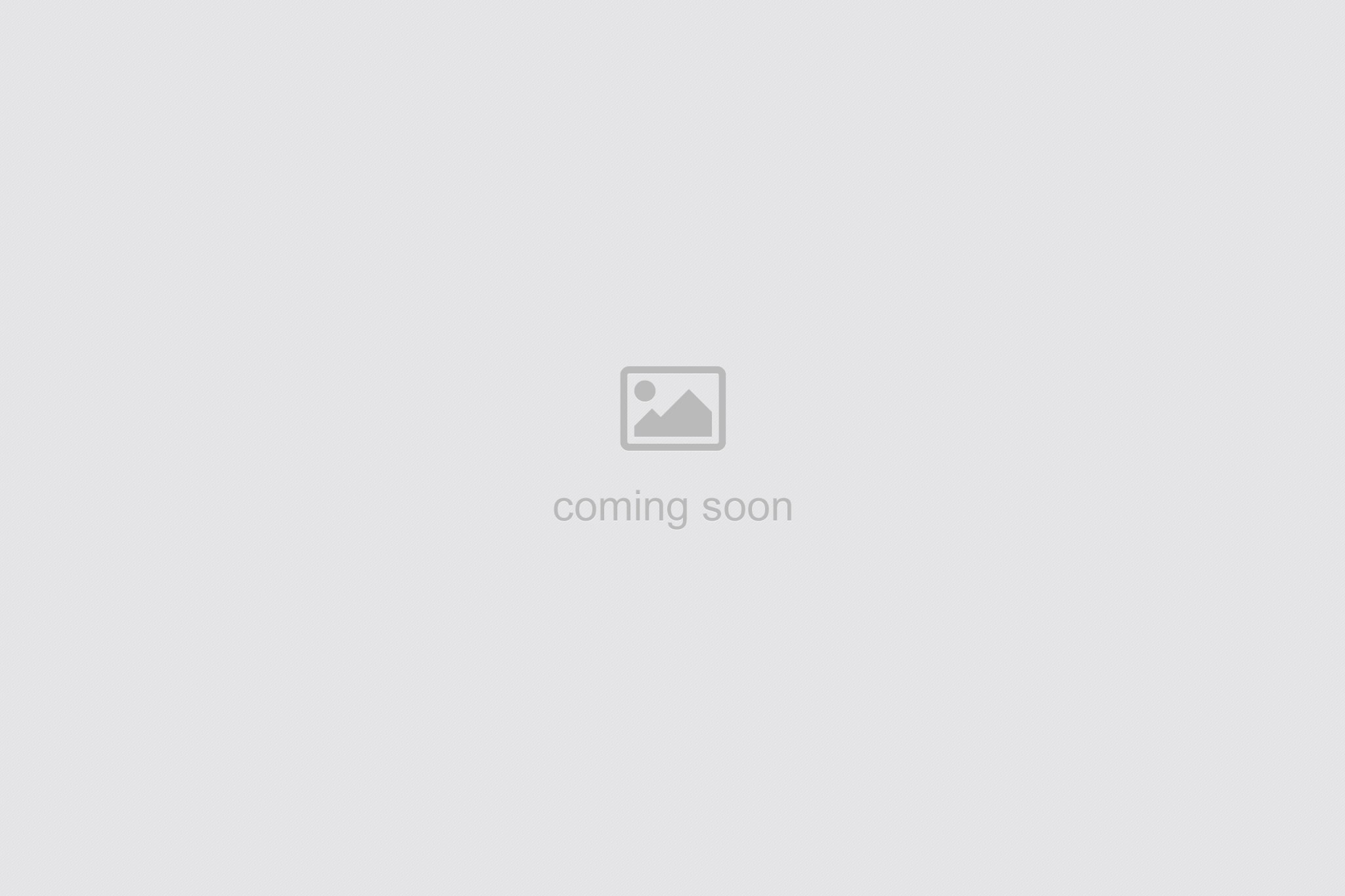| 設置者 | 佐久市 |
指定管理者 |
社会福祉法人恩賜財団済生会支部長野県済生会 |
| 施設長名 | 小林 一三 |
| 定員 | 長期入所 80名、短期入所 20名 |
運営目標
1.使命の追求
○生活困窮者への援助の積極的推進
・第1期中期事業計画に引き続き、生活困窮者、介護虐待等の社会的弱者の受け入れについては、他関係機関と連携して対応していきます。
・社会福祉法人利用者負担軽減制度等の対象者については、行政より依頼があれば積極的に受け入れを行っていきます。
○総合的な医療・福祉サービスの提供
第1期中期事業計画に引き続き、他団体との連携を更に強化し、包括的なサービス提供体制を充実させます。
2.新たな分野への挑戦
○医療・福祉の周辺分野への取り組み
・地域民生児童委員会の開催の場の提供
・地元開催のいきいきサロンへの積極的参加
・相互の能力向上のための、介護事業所における情報交換
・岩村田・東地域包括支援連絡会の場の提供
・認知症予防教室「いきやしょみつい」の開催
○まちづくりへの寄与
少子高齢化に伴い、地域住民が住み慣れた地域で安心安全に暮らし続けることができるよう、福祉エリアとしての立地
条件を生かし近隣施設と連携し、途切れの無いサービスの提供に努めます。
3.経営基盤の健全化
○経営の健全化
第1期中期事業計画と同様に、増収策及び費用削減策を引き続き進めていきます。
・利用率を長期97%、短期90%以上にします。
・算定な可能な加算については、検討し算定できるように努めます。
・今後の経営安定のためにコンサルティング会社に委託し、中長期事業計画の策定を進めています。
・空調設備の熱源をEHPに改修し、熱源コストの削減を図ります。
・共同購入ができる物品については、検討し、進めていきます。
・適正な人員配置により、人件費の削減に努めます。
・居宅介護支援事業所のニーズや施設に対する要望を把握し、利用者の受け入れを積極的に行っていきます。
○医療・福祉サービスの質の向上
・済生会を支える人材の育成
県社協が実施している外部研修の福祉職員生涯研修と併せて、内部研修制度である「段階別育成プログラム」を整備し、全職員が職種・経験年数に応じてスキルアップする仕組みを構築します。
また、介護人材不足が慢性化する中で、長期履修制度を活用し介護人材確保に努めると共に、高等学校等への呼びかけも強化していきます。
・スケールメリットを活用した取り組みの推進
済生会による「共同購入を利用することにより、引き続き経費削減に取り組んでいくと共に、今後は電子血圧計、体温計についても、共同購入をしていきます。
○積極的経営の推進
佐久市の人口減少に伴い、要介護認定者が減少している中で、利用率を維持・向上するための方策が今まで以上に重要 となってきます。また、平成30年4月の介護報酬改定による減収も、念頭に以下の事に努めます。
・引き続き、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等に空き情報の提供を行っていきます。
・短期入所の緊急受け入れについては、積極的に行っていきます。
・居宅介護支援事業所等にアンケートを取り、施設に求める事を洗い出し、対応をしていきます。
・済生会共同購入の採用物品については、施設で購入している物は採用し、経費削減に努めます。
4.済生会ブランドの確立と発信
広報については、引き続き年3回発行します。また、ホームページの更新についても、随時対応していきます。
5.コンプライアンスの徹底
第1期中期事業計画に引き続き、毎年コンプライアンス研修を開催し、全職員が法令遵守や内部統制の重要性について理解を深めるよう努めます。
6.国際連携の推進
地域の福祉大学においても外国人学生を受け入れ、または、研修を行っている大学もあるため、施設としても外国人介護職員(介護福祉士)の受け入れ態勢を研究し、雇用につながるよう検討を進めます。
7.災害対策の推進
・地震等の自然災害の想定の防災訓練を繰り返し実施することで、緊急時の対応がスムーズに行えるように努めていきま
す。
・防災マニュアル、豪雪マニュアル等は随時見直しを行っていきます。
・DCATの登録職員については、随時募集を行い体制を整え、全国で協力体制を取ります。
・災害の際の地域住民との連携を図っていきます。
・災害時の施設の受け入れについては、柔軟に対応して行きます。
【介護老人福祉施設】
目的
シルバーランドみついは、旧三井小学校の跡地に設置され、周囲を木々に囲まれ豊かな自然環境に恵まれています。また、保育園や児童館などの児童福祉施設や地域のみなさんが集う世代交流館、さらにグループホームが隣接し、高齢者福祉の向上に配慮した安全で快適な環境が整えられています。
シルバーランドみついは、多年にわたり社会の伸展に貢献されてこられた入所者を敬愛し、健全で安らかな生活を保障することを基本理念として、適切な介護サービスを提供し、人生の完成期を心豊かにお過ごしいただけるような施設運営を目指します。
さらに、家族(会)との連携を図りながら、地域、ボランテイア等との交流を積極的に行うことにより、地域社会へ参加をしていくものとします。
シルバーランドみついは、多年にわたり社会の伸展に貢献されてこられた入所者を敬愛し、健全で安らかな生活を保障することを基本理念として、適切な介護サービスを提供し、人生の完成期を心豊かにお過ごしいただけるような施設運営を目指します。
さらに、家族(会)との連携を図りながら、地域、ボランテイア等との交流を積極的に行うことにより、地域社会へ参加をしていくものとします。
行事予定
| 月 | 行 事 |
| 4月 | お花見、いちご狩り、誕生日会 |
| 5月 | 誕生日会 |
| 6月 | 運動会、誕生日会 |
| 7月 | 夏祭り、誕生日会 |
| 8月 | 誕生日会 |
| 9月 | 敬老会、誕生日会 |
| 10月 | そば打ち、誕生日会 |
| 11月 | すしバイキング、誕生日会 |
| 12月 | クリスマス会、誕生日会 |
| 1月 | 誕生日会 |
| 2月 | 節分、誕生日会 |
| 3月 | すしバイキング、ひな祭り、誕生日会 |
クラブ活動

生け花クラブ

書道クラブ

模擬喫茶

おやつクラブ
ボランティアによる活動

音楽療法
歌をとおして季節を感じ、体を動かしながら大きな声で歌を歌うことで、心も体も元気になるように「ひまわりの会」の皆さんにより、毎月1回、音楽療法を行っていただいています。
歌をとおして季節を感じ、体を動かしながら大きな声で歌を歌うことで、心も体も元気になるように「ひまわりの会」の皆さんにより、毎月1回、音楽療法を行っていただいています。
心のいやし事業

佐久地域21寺院23名の住職さんで組織された「佐久仏教会・シルバーランドみついの会」の皆さんが、居室訪問・お話の会(法話)・行事への参加をしていただいています。
居室訪問では、入所者の話し相手になって、心配ごとなどの相談にものっていただいています。
また、月1回の法話では、人生論をはじめ自由なテーマでお話いただき、時には笑いのある話の中、入所者の皆さんは、次回の来訪を心待ちにしていると共に、入所者の家族の皆さんの参加もあります。
居室訪問では、入所者の話し相手になって、心配ごとなどの相談にものっていただいています。
また、月1回の法話では、人生論をはじめ自由なテーマでお話いただき、時には笑いのある話の中、入所者の皆さんは、次回の来訪を心待ちにしていると共に、入所者の家族の皆さんの参加もあります。
【短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護】
目的
シルバーランドみついは、短期入所生活介護の利用を希望される方が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、施設において適切で快適な短期入所生活介護サービスを提供し、利用者の在宅生活と家族の生活支援を行います。
また、要支援1、2と認定された利用者に対しては、介護予防サービス支援計画表をもとに、利用者・家族の意向にそった支援を行っていきます。